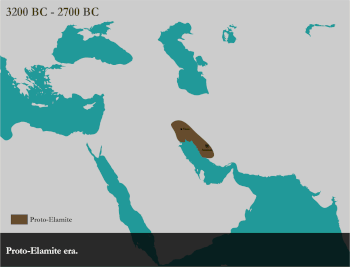
エラム (Elam, 紀元前3200年頃~紀元前539年)
古代オリエントで栄えた国家、または地方名。紀元前3200年頃~紀元前539年に複数の古代世界の列強国を出現させた。
概要
エラムと呼ばれたのは、メソポタミアの東、現代のフーゼスターンなどを含むイラン高原南西部のザグロス山脈沿いの地域である。エラム人自身は自らをハルタミ (Haltami) と呼び、土地を指す際にはハルタムティ(Haltamti、後に訛ってアタムティAtamti)と呼んだ。シュメール語のエラムはこれの転訛したものである。
- メソポタミアという古代文明世界の中心地に隣接したために、その文化的影響を強く受けたが、砂漠や湿地帯によって交通が困難であったために、政治的にはイラン高原地帯との関わりが深かった。
- エラム人は系統不明の言語エラム語を話す人々であり、メソポタミアでウルク古拙文字(楔形文字の元になったと考えられている絵文字)が発明されてから程ない紀元前3000年紀頃よりイラン高原でも絵文字のような記号が使われるようになった。これはイラン高原で最初に活動を開始したエラム人が使用したものと考えられ、そこから変化したと思われる線文字も見つかっており「エラム線文字/原エラム絵文字」と呼ばれている。かかる原エラム文字で書かれた文章は現在のアフガニスタンに近い地域からも見つかっており、エラム文化はイラン高原各地に影響を与えていたと考えられているが、まだ解読されておらず、シュメール人の文字との関係も不明である。またほぼ同時代にエラム語楔形文字も使われているが、これらの関係は全く解明されていない。
エラム語は膠着語であり、その近隣で話されていたセム語族やインドヨーロッパ語族の言語とは近縁関係にない。エラム語はシュメール語と「姉妹」語であると主張する人もいる。
- ロバート・コールドウェルは1913年にベヒストゥーン碑文のエラム語とドラヴィダ語との比較を行い、フェルディナンド・ボルク(1924年)はエラム語が現在インドで話されているドラヴィダ語系のブラーフーイー語と関係があるとの説を提唱し、これらの説を継承したデイビッド・マカルピンは言語学的分析を行なっている(エラム・ドラヴィダ語族)。
- またドラヴィダ語族とウラル語族、アルタイ諸語の間には文法の著しい類似性が存在し、このことは両者が共通の起源より派生していることを示唆する。
両者の共通祖先としてエラム語の存在を位置づけることができるかもしれない。
メソポタミア諸王朝はたびたびエラムに侵入して、これを支配下に置いた。一方エラム人もメソポタミアへの介入を繰り返し、バビロニア諸王朝を幾つも滅ぼしている。
- 紀元前2000年紀に入ると、エラム人もシュメール人やバビロニア人に倣って楔形文字を使って記録を残すようになり、多くの情報が後世に伝わる。エラム史で中心的役割を果たした都市はアンシャン、そしてスサである。スサを中心とした地方はギリシア人たちにはスシアナとよばれた。
- エラム人は、オリエントのほかの地域とは異なる独特の相続制度を持っていた。即ち、王位は親子ではなく、まず兄弟によって相続されていくのである。この相続制度はかなり後の時代にまで継承され、異民族の侵入によっても基本的に変化しなかった。
その歴史は他のオリエントの地域と同じく言語(文字)史料の分類に基づいて区分されている。
原エラム時代(プロト・エラム時代, 主に紀元前3200年頃~紀元前2700年頃)
この時代既に原エラム文字による文字記録が存在するが、原エラム文字の解読が進んでいないため、基本的には考古学情報に頼って再考される。既にスーサなどの都市が形成されていた。
古エラム時代(古王国時代, 紀元前2700年頃~紀元前1600年頃)
原エラム時代とまとめて扱われる事もある。紀元前2700年頃のアワン王朝の成立から紀元前1600年頃のエパルティ(スッカル・マフ)王朝の滅亡まで頃とされる。
文字記録が多く残され始める時代であるが、その後半期は衰退の時代であったと推測されている。
エラム人は最初紀元前24世紀のアッカドのサルゴン王の碑文などに現れ、たびたび侵攻される様になる。
エラム人側もメソポタミアにたびたび侵攻した事が碑文に遺されており、紀元前22世紀にはスサ地方に進出して、王朝国家を建国した。
紀元前2004年頃にはメソポタミア南部に侵入してウル第3王朝を滅ぼし、紀元前18世紀にはバビロン第一王朝のハンムラビ王と抗争した。
近年ではエラム人が直接の関係を持たなかったインダス文明(紀元前2500年頃~紀元前1500年頃)とメソポタミア文明の橋渡しをした可能性が指摘される様になりました。
<青柳正規『人類文明の黎明と暮れ方』2009初刊 2018講談社学術文庫版再刊 p.238-240>
最近、シュメール人のメソポタミア文明と接触していたエラム人は、その東にあったインダス文明との間にあり、直接は関係がなかった両文明を仲介する働きをしていたのではないか、との学説が出されている。
- エラムの最初の居住地は地下資源が豊富で、シュメールからの独立を維持していたが、紀元前2600年頃、その地下資源を狙ったシュメールの侵攻を受け、都を東のアラッタに移した。
- それはイラン高原東南部、現在のケルマーン州にあったので、インダス文明圏とも接触。このアラッタを中心に「トランス=エラム文明」とも言われる交易圏が成立、石材や木材、クロライトという綠泥岩の加工品、アフガニスタン特産のラピスラズリなどがメソポタミアにもたらされたと考えられている。
ラピスラズリ (lapis lazuli) は、方ソーダ石グループの鉱物である青金石(ラズライト)を主成分とし、同グループの方ソーダ石・藍方石・黝方石など複数の鉱物が加わった類質同像の固溶体の半貴石である。和名では瑠璃(るり)といい、サンスクリット語のヴァイドゥーリャないしパーリ語のヴェルーリヤの音訳である。深い青色から藍色の宝石で、しばしば黄鉄鉱の粒を含んで夜空の様な輝きを持つ。
- 新石器時代からアフガニスタンで採掘され、地中海世界と南アジアに輸出された。パキスタンにある紀元前7千年期のインダス文明-アフガニスタン間の重要な交易路であった新石器時代の遺跡メヘルガルからはラピスラズリのビーズが発見されている。これらのビーズは紀元前4千年紀のメソポタミア文明北部の入植地などでも発見されている。
- 古代社会でラピスラズリを特に高く評価したのはエジプトで、ファラオ、王族、神官などの祭司階級しかこの石をつけられない時代もあったという。歴代のファラオに尊ばれ、黄金に匹敵するほどの価値を与えられることもあった。
この様に人類に認知され、利用された鉱物として最古のものとされている。エジプト、シュメール、バビロニアなどの古代から、宝石として、また顔料ウルトラマリンの原料として珍重されてきた。日本ではトルコ石と共に12月のほかに9月の誕生石とされる。主成分にもラピスラズリとは異なる日付が誕生石として設定されている。
- ラピスはラテン語で「石 (Lapis)」、ラズリはトルキスタンにあるペルシア語地名 "lazhward"(ペルシア語: لاژورد、現在のアフガニスタン・イスラム共和国バダフシャーン州en:Kuran wa Munjan DistrictにあるSar-i Sang鉱山の古名)が起源で、それがアラビア語に入って "lazward"(アラビア語: لازورد、ラズワルド: 天・空・青などの意でアジュールの語源)で「群青の空の色」を意味する。すなわちラピスラズリ (lapis lazuli) は、ラテン語で「lazhwardの石 」を意味する。
- 古代ギリシャでサプフィールといったのは、今のサファイアではなくラピスラズリであったという説もある。
- 旧約聖書の出エジプト記の、祭司の装飾品のひとつである胸当てにはめ込む「青い石(Sappir)」は、ラピスラズリだといわれている。また新約聖書のヨハネ黙示録では、世界が終末を迎えた後現れるとされる新エルサレムの都の神殿の東西南北12の礎にはそれぞれ12種類の石で飾られ、そのうちの2番目がサファイア、11番目が青玉と記述されているが、青玉は現在ではサファイアのことを指すので、もしそうであれば2番目のサファイアはラピスラズリのことを指している可能性がある。この他にも旧約聖書でモーセがシナイ山にて、神より授かったとされるモーゼの十戒が刻まれた石版はサファイアとされていたが、これもラピスラズリであったといわれている。
- 日本では、ラピスラズリは瑠璃と呼ばれ、仏教の七宝のひとつとされ、仏典『無量寿経』や『法華経』に瑠璃の記述がある。奈良の正倉院の宝物庫には紺玉帯と呼ばれるラピスラズリで飾られた黒漆塗の牛革製ベルトが収められている。
このアフガニスタンのラピスラズリの鉱山をキリスト教徒として初めて訪問したのは、フビライ汗とローマ法王の親書をたずさえた1271年のマルコポーロ一行であった。ここの採掘はバラシャン国の王の直轄でなされており、外国人は入山禁止になっていて実際、潜入しようとして警備兵に殺された者もあった。史上に残るその後の外来訪問者はイギリスの地理学者ジョン・ウッドで1838年のことであった。
この様に大河の流域ではない地域に交易という形で文明が形成されたことが明らかになり、従来の文明観の再検討が必要になっている。
<『世界四大文明 インダス文明展図録』2000 NHK p.153>
紀元前2350年頃のメソポタミアのサルゴン王の碑文(楔形文字の押された粘土板)に、「メルッハの船、ディルムンの船、マガンの船を波止場につないだ」という記載がある。別の文献では「メルッハから金、銀、銅、紅玉髄、黒檀などがもたらされた」とある。このメルッハが、インダス文明を意味し、メソポタミア文明にとって重要な交易相手であったと考えられている。
メルッハについての記載は、紀元前1800年頃にはあまりみられなくなる。この頃にインダス文明は衰退したと考えられている。インダス文明は、メソポタミアやペルシア湾地域と活発に海洋交易を行った文明である。ドーラビーラーやロータルは、そのための拠点となる都市であった。
さらにはこんな話も。
最近ではフェニキア商圏存続期(紀元前10世紀頃~紀元前1世紀頃)に地中海沿岸一帯を席巻した「黒い地母神」の起源について、フェニキア商人がインド南岸のドラヴィダ系のタミル人が信仰していた「破壊神カーリーの原型」を借用したとする説が浮上している。そもそもエラム人なら同じエラム・ドラヴィダ語族(Elamo-Dravidian languages)のインダス文明(紀元前7000年~紀元前1800年)と交流があった訳で、そちら経由の可能性もある。

そういえばインダス文明の都市遺跡ハラッパーでは紀元前2000年頃のブロンズ製チャリオットと運転手が出土していますね。

そして紀元前1500年頃には「戦車を駆る」アーリア人がインドに侵攻…
中エラム時代(紀元前1600年頃~紀元前1100年頃)
紀元前1600年頃のイゲ・ハルキ朝の成立から紀元前1100年頃の、イシン第2王朝のネブカドネザル1世によるエラム侵攻までの時代である。なお古エラム時代のとの境目には諸説ある。
古エラム時代末期の衰退期から再びエラムが列強として登場する時代であり、バビロニア文化の影響を強くうけた時代である。カッシート朝(バビロン第3王朝)を滅ぼしたが、最後にはネブカドネザル1世の侵攻で大打撃を被り、再び衰退した。
<山本由美子『オリエント世界の発展』1997 中央公論新社 世界の歴史4 p.81-92>
紀元前12世紀にはスサを都とした新王朝が成立、メソポタミア中央部に入り、紀元前1155年カッシート王国(バビロン第3王朝)を滅ぼし、オリエント最大の軍事勢力となった。
バビロニアの諸都市を征服したエラム王国の王は、バビロンを都としたハンムラビ王の遺品をスサに持ち去った。ハンムラビ法典の記された石碑もこのとき持ち去られたのであり、それがバビロンの遺跡ではなくイランのスサで発見されたのはそのような事情があったからである。
<小林登志子『シュメル-人類最古の文明』2005 中公新書 p.270-271>
紀元前13世紀頃のエラムの王が建設したとされるのが現在のイランの南西部(フーゼスターン州シューシュ)に残るチョガ・ザンビールに残るジッグラトである。
1935年に油田探索の調査飛行中に土で出来た不思議な塔が発見され、調査の結果ジッグラトであることが判明した。現在は発掘調査が終わり、復元され、世界遺産に登録されている。
一辺105mで四隅が東西南北を指し、五層からなる高さ約28mの最大のジッグラト。それ自体はメソポタミアのシュメール人起源でイランのものではないが、ウル第3王朝を滅ぼしたエラムが継承したものと考えられる。
メソポタミアでは紀元前1155年、カッシト朝バビロニアがエラムによって滅ぼされたが、翌年イシン第2王朝(紀元前1157年~紀元前1025年)が勃興、その王であるネブガドネザル1世がエラムに侵攻して短期間ながら首都スーサを支配した。しかしネブガドネザル1世死後、アラム人らが侵入を開始、バビロンを代表とするバビロニア諸都市は壊滅的打撃を受けた。そして以降第2海の国、バジ王朝、エラム王朝などが勃興を繰り返し、バビロニアは事実上暗黒時代を迎える。
一方(シュメール人やバビロニア人に倣って紀元前2千年紀頃より楔形文字を使用する様になり、インダス文明とメソポタミア文明を仲立ちする存在になったと考えられている)エラムは隆盛期を迎えており、ウンタシュナピリシャがチョガザンビルに巨大なジッグラトを建設、さらには紀元前12世紀末シュトルクナフンテがメソポタミアを攻撃、ハンムラビ法典を代表とする戦利品をスーサに運び去り、その子クティルナフンテがイシン第2王朝を攻め滅ぼした。
以降、バビロニアでは強力な中央権力が存在せず、多くの短命王朝が興亡する不安定な状況が続く。バビロニアの政治的・神学的中心都市はバビロンであり「バビロンの王」がバビロニア王とみなされたが、実際には、諸都市は独立状態にあった。さらに、元々遊牧民であったアラム人やカルデア人といった諸部族がバビロニアに定住し、特に(後にその天体観測技術や暦法でギリシャ人の称賛の的となる)カルデア人が政治的に重要な役割を果たす事になるのである(カルデア王朝/バビロン第11王朝,紀元前625~紀元前539年)。ちなみにバビロン第7王朝はエラム人の一代王マール・ビティ・アプラ・ウツル(在位紀元前983年~紀元前978年)が開闢し「エラム王朝」と呼ばれる。
新エラム時代(紀元前1100年~紀元前539年)
紀元前1100年のネブカドネザル1世の侵攻から、紀元前539年にアケメネス朝の支配下に入るまでの時代であり、研究においては更に3期に細分される。
紀元前12世紀末頃より弱体化が始まり、記録から姿を消す。紀元前640年にアッシリア帝国のアッシュール=バニパル王によって破壊され滅亡した。
紀元前7紀末までに、スサを中心としたエラム人の地域は北方のメディア王国の支配下に入り、その後は独立することはなかったが、エラム人の残した文化や優れた行政制度や官僚機構はメディアやペルシアにも採用され、エラム語は公用語の一つとされてアケメネス朝の中ごろまで使われた。またエラムの都だったスサは、アケメネス朝でも諸官庁が置かれる政治上の都として続いた。
なんとも複雑怪奇な文化継承関係…
