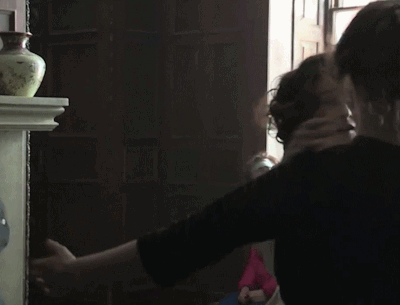ここで第一次世界大戦(1914年~1918年)前夜、すなわち南北戦争(1861年~1865年)、戊辰戦争(慶応4年/明治元年(1868年)~明治2年(1869年))、普仏戦争(1870年~1871年)、マフディーの反乱(1881年~1899年)、日清戦争(1894年~1895年)、ボーア戦争(1899年~1902年)、義和団の乱(1899年~1900年)、日露戦争(1904年~1905年)、辛亥革命(1911年~1912年)があった時代を振り返っておきましょう。
英国、スイス、ベルギーなどにおいては産業革命の導入が自然発生的に進行しましたが、(革命とナポレオン戦争の焼け跡からの再出発となり「馬上のサン=シモン」ナポレオン三世が再建を手掛けた)フランス、(南北分断状態の克服を必要とした)アメリカ、(ハプスブルグ君主国からの独立を必要とした)ドイツ帝国とイタリア王国、(江戸幕藩体制からの脱却を必要とした)日本の場合はそれに先立って流血の痛みを伴う「主権国家への移行」過程を必要としたのでした。
ガトリング砲は1861年にアメリカ合衆国の発明家リチャード・ジョーダン・ガトリングが製品化した最初期の機関銃である。前装式小銃が主流だった南北戦争当時、ガトリング砲の持つ200発/分の連射速度は驚異的であり、1866年に軍によって採用される以前から、セールスエンジニアが戦場にガトリング砲を持ち込み、実際に敵兵(南軍)を撃って見せる実戦参加デモンストレーションが行われてきた。しかしやがて南北戦争で双方が使用したエンフィールド銃に代表されるミニエー式小銃の強力な殺傷力が、戦列歩兵式の歩兵運用を廃れさせてしまう。歩兵が「密集して真っ直ぐ向かってくる存在」から「散開しながら接近してくる存在」に変貌すると、機動性と軽便さに欠けるガトリング砲は徐々に野戦における有効性を失っていったのである。またその射手がクランクを回して操作するために射撃姿勢が高く、狙撃を受けやすいという問題もあった。
一方、ガトリング砲がその威力を発揮するのは敵兵が突撃を仕掛けてきた際の拠点防衛用や海戦においてであり、敵艦の甲板を掃射して乗組員を殺傷したり、接舷攻撃を仕掛けてきた敵を迎え撃つ役割には大変適していた。その事に注目した大英帝国や帝政ロシアの海軍は、植民地での海賊撃退用にこれを活用している。
日本の機関銃の歴史は幕末に手動式のガトリング銃を購入した事に始まる。3丁輸入されたうち2丁を長岡藩が購入し、戊辰戦争で官軍相手に奮戦。一応は官軍を混乱に陥れたもののあまり役には立たなかったともいわれている。何しろ重いし手動回転なのでどうしても照準が狂ってしまう。結果として兵士1人を倒すのにかかる銃弾がやたらと多くなりワリが合わない。そもそもこの当時の日本では歩兵全員が銃を持っていたわけではなかったし、ガトリング銃は口径が1インチ(25.4mm)もあったので、弾だけでも調達するのにやたらと金と手間と資材がかかった。何しろ当時の長岡藩に近代的溶鉱炉がある筈もなく、さらには日本では火薬(黒色火薬)の75%を占める硝石が産出しないので火薬の調達もままならなかったのである。
話はプロイセンの銃工ヨハン・ニコラウス・フォン・ドライゼの手になる世界初の実用的ボルトアクション後装型小銃ドライゼ銃(Dreyse Zündnadelgewehr,開発1824年~1836年、制式採用1841年)の発明にまで遡る。先進的過ぎた為に当初はほとんど注目されなかったが、国土拡張戦略に転じたプロイセンが1860年代に活用。普墺戦争(1866年)におけるケーニヒグレーツの戦い(Schlacht bei Königgrätz)などを勝利に導く原動力となり、その名声を全世界に轟かせた。ドライゼが爵位を受けたのも1864年になってからである。
この銃は射手が地面に伏せた姿勢で敵の弾丸を避けながら、一体化した薬莢で簡単に再装填を行って、射撃姿勢を維持しながら前装銃とは桁違いの速度で持続射撃を続ける事を可能とし、その普及は太古から一貫して「立って歩き、立って射撃する存在」だった歩兵の運用を「戦場を匍匐前進する存在」へと変化させてしまった。
実際、普墺戦争(1866年)においてこの銃を装備したプロイセン兵は、射程では優る先込め式銃を使っていたオーストリア兵が次の一発を放つ為に立ったまま次弾を再装填する間に地面に伏せたまま5発(さらにはそれ以上)を発射して敵をなぎ払ったとされる。
あまりに気に入ったのでこの銃をこの時代まで使い続けたプロイセン軍に対してフランス軍歩兵は、当時の世界で量産されていた火器としては最新式といえる同じ後装式のシャスポー銃(Chassepot、正式にはFusil modèle 1866。1866年制式)を装備した。
この銃はガス漏れ防止ゴムリングと小さめの弾丸の採用によってドライゼ銃(最大射程550m)の倍以上の最大有効射程約1500mを誇り、さらに装填時間も短かった。
イタリア統一運動(Risorgimento, 1815年~1871年)の一環をなすメンターナの戦い(Battle of Mentana,1867年11月3日)においてプロイセンと同盟していたガリバルディ軍を叩き潰してフランス議会に「Les Chassepots ont fait merveille!(シャスポー銃は見事にやってくれました!)」と報告されたのが初陣となった。それに先駆けて慶応2年(1866年)12月にナポレオン3世が2個連隊分(1,800丁~2,000丁)を江戸幕府に無償提供。幕府も当時の最新鋭であったこの武器を大名・旗本に売り込むため10,000丁ほど注文している。またファーブル・ブランド商社を経由して、独自にシャスポー銃を1,600丁の購入を計画していた藩も存在した。
この時代には薩摩藩が戊辰戦争期に大英帝国で採用されたスナイドル銃がを大英帝国経由で導入。実際の導入数こそ少なかったものの、その完成度の高いボクサーパトロンの蝶番型銃尾が防水・防湿性に優れた密閉構造だった為に多湿・多雨な日本や南・東南アジア(当時の大英帝国植民地)でも問題なく着火する信頼性を発揮。簡単な加工で前装銃を後装式に改造できた為に、既に多数輸入されていたエンフィールド銃が日本国内でもその改造を施された(事実、当時の鉄砲鍛冶は旧々式化していた数百年前の種子島式火縄銃までも後装銃に改造している)。一方、シャスポー銃は、フランス語通詞が少なかったために教範(取扱・運用説明書)の日本語訳すら完了しておらず、遠く離れたフランス本国で製造される専用弾薬の供給も困難であり、薬莢の構造と日本の気候の相性が悪く不発が多かったこともあって全く有効活用されず、一説には江戸城開城の際に手付かずの状態で蔵に残されていたとさえいわれている。その一方で大鳥圭介率いる幕府陸軍の精鋭部隊伝習隊がシャスポー銃を使用していたという記述も散見される。これを真っ向から否定する研究者もいるが、雨が多く湿度の高い日本で紙製薬莢の扱いに苦労したり、不足した専用弾薬を大鳥が日本で作らせたがうまくいかなかった等の記録が残っている事から、伝習隊がシャスポー銃・ドライゼ銃といった紙製薬莢を使う後装式銃を一時期であれ使用していた事自体は否定出来ない。
この様な事情から明治新政府は日本陸軍創建にあたって、紙製薬莢の問題とゴム部品の調達に難があって信頼性に欠けるシャスポー銃を主力小銃に位置付けなかった。しかしながら原産国のフランスでシャスポー銃から金属薬莢式のグラース銃への改造が行われる様になった明治7年(1974年)頃からシャスポー銃のボルトに嵌めるゴム部品の品質や購入についての記録が散見されるようになる。そして明治10年(1877年)の西南戦争では村田経芳少佐がドイツの企業に依頼してシャスポー銃を金属薬莢式に改造する計画を進めていた事が記録に残り、国産小銃13年式村田銃の試作過程ではグラース銃が参考にされ、多くの構造を継承する展開を迎えたのだった。

またフランス軍はライフル弾を用いた多銃身斉発砲ミトラィユーズ(Mitrailleuse)を配備していた。最古のそれはガトリング砲発明に先駆けた10年前に登場。1851年にベルギー陸軍大尉のトゥサン=アンリ=ジョゼフ・ファフシャンが発明した。続いてモンティニー ミトラィユーズが1863年に発明され、そして1866年フランスにおいてレフィエ・ミトラィユーズの名で知られる25砲身の"Canon à Balles"が重要機密として採用された。これが陸軍で大規模戦争中に制式装備として運用された初の連射火器であり、普仏戦争に投入されたのである。
鋼製のブロック内に25発の13mm(.51口径)センターファイア式実包を収容し、射撃前に薬室に対して固定された。手動操作式でハンドルを回せば25発の弾丸が立て続けに射出される。レフィエ・ミトラィユーズの場合、実現可能な発射レートは100発/分、有効射程はおよそ2000ヤード(約1.8km)でありドライゼ銃を大幅に上回った。
ただしレフィエ・ミトラィユーズは6門の砲列で運用され、砲兵員によって操作された。つまり歩兵支援火器ではなく特殊な火砲の一種として運用されたのである。その革新性と良好な弾道特性にもかかわらず基本概念と運用法に欠陥があった事、また普仏戦争開戦時点で210門しか存在しなかった事ことからこの機関銃の元祖は戦術兵器として歴史に名を残せなかった。ガトリング砲が電動化されて広汎な成功を収め、今日まで生き残っているのに対して普仏戦争に敗れたフランス陸軍はあっけなくにその野戦での運用を1871年に打ち切っている。ただしMitrailleuseという言葉自体は機関銃を示す一般的な言葉としてフランス語に定着する事になったのである。
こうした不利を跳ね返したのがプロイセンの火砲と兵力動員能力の優位だった。
- プロイセン軍の砲兵隊には(その前身たるC-64が普墺戦争の時点では信頼性が充分でなく、戦場でしばしば爆発事故を起こした事から当初プロイセン軍将校達の不興を託った)鋼鉄製で後装式のクルップC-67野砲(弾丸重量3kg)が供給されており、これはドライゼ銃の欠点を補って余りあるものがあった。亜鉛玉と爆発物を詰めた接触雷管(contact-detonator)式の弾丸を発射するクルップ砲は(ちゃんと機能するなら)射程距離4500mで、フランスの青銅製の前装砲よりも猛烈な発射速度を誇っていたのである。
- またプロイセン軍は常備兵ではなく徴兵で構成されていた。1859年から1873年までプロイセン国防大臣を務めたアルブレヒト・フォン・ローンが1860年代にプロイセン軍制に一連の改革を実施した結果、普仏戦争に参戦したドイツ諸邦の合計人口(約3200万)はフランスの人口(約3800万)をおよそ600万も下回っていたにもかかわらず、兵力においてはフランスのそれをおよそ5万人上回る(55万人VS50万人)動員が可能となったのである。
- さらには動員制度にも格段の差があり、プロイセン側が462,000人の兵士を完璧にフランスの前線に送り込んだ一方(そのうち38万人を18日間で動員し、さらに9万の兵力を対オーストリア用に温存)、計画の杜撰さと管理のせいでからフランス側は最初から100,000人の兵を活用できない状態にあった事もあり(プロイセン側の各軍団が主要都市周辺に基地を設営し、連隊基地へ行くのに1日以上旅行せねばならない場所に住んでいる予備役兵がほとんどいなかったのに対し、革命が相次いだ歴史から軍が反乱軍となるのを恐れた帝国政府が軍を民衆から隔離する為に連隊を自らの兵を徴募する地域に駐屯させておらず、多くの応召兵がまず数日旅行して所属連隊の補給処に出頭してから更に長旅を経て所属連隊の駐屯地へ向わねばならなかった)270,000人しか前線に送り込めなかった。実際戦争開始時のフランスにおいては実に歩兵100個連隊中のうち65個連隊が補給厰から遠く離れた駐屯地にあり、鉄道駅の多くが応召兵で埋め尽くされて無為に軍糧と命令を待つばかりだったのであったとされる。
- またプロイセン参謀本部は、鉄道網を活用した分刻みの動員計画を用意しており、その鉄道網の一部が参謀本部鉄道課の勧告に従って敷設されたものであったのに対し、フランスの鉄道網は複数の民間鉄道事業者の競争を背景に純粋に商業的な理由により敷設され発展してきたものだったので、アルザス=ロレーヌの前線に向かう移動すら多くの場合、大幅な迂回や頻繁な乗り換えを必要とした。さらには軍が列車を統制する仕組みが全くなく、将校が適当だと考えた列車を単純に徴用して使う方式だったので操車場が兵を載せた貨車で埋め尽くされて身動きが取れなくなり、しかも兵を下車させたり、正しい目的地へ出発させたりする事について責任を負う者が誰もいなかったのである。
それでも既に強力な常備軍を十分現地に配備していたフランス側は開戦当初こそ実働兵力と実戦経験の面で優位に立ったが、シャスポー銃とミトラィユーズのドライゼ銃に対する射程優位を生かして塹壕戦を防御的に戦わんとしたその戦術構想自体は、さらなる長射程を誇る砲兵の攻撃的運用と動員人数上の優位を生かして包囲形勢を構成せんとしたプロイセン側の戦術構想に脆くも破れ去る展開を迎えてしまう。かかる先例を受けて大日本帝国も国民皆兵制導入を決断。(伝統的幕藩体制の延長線上で国土を軍事貴族が分割掌握する体制を提唱した一部氏族が士族反乱鎮圧鎮を経て実戦経験を積んだ台兵によって粉砕された)西南戦争(1977年)が戦われる事になったのである。
ちなみにポール・ヴィエイユ(Paul Vieille)が綿花薬=ニトロセルロース(nitrocellulose)をエーテルとアルコールの混合液でゼラチン化した実用火薬を発明したのが1880年。当時の陸軍大臣ブーランジェ将軍の頭文字からB火薬と命名されて1886年までに実用化された。また19世紀後半~20世紀初頭に真鍮製の薬莢が出現し,これによって105mm級以下の小口径の火砲は,可塑性の緊塞具を閉鎖機に装着しなくてもガス漏れを防ぐことができるようになり,また装薬を詰めた薬莢を弾丸の尾部に接続して一体の完全弾薬とすることによって弾丸装塡および発射の速度を増大させたのである。黒煙が射界を塞がないのが飛躍的進歩であり、無煙火薬と呼ばれることになった。また後に写真や映画を登場させるメディア革命を支えたセルロイド・フィルムの登場もこの時期のセルロースを巡る技術革新の副産物の一つであった。
キッチナー将軍いる大英帝国軍は、マフディー軍との戦いにおいて徹底して殲滅戦を展開したが、この時世界で初めて機関銃が使用されたのである。
1884年には英国生まれの米国人発明家ハイラム・マキシムが世界初の全自動式機関銃マキシム式機関銃(Maxim gun, 1884年)を発明。同時に世界各国に売られ第日本帝国へも明治20年(1887年)に輸入されている。後には無断コピーも生産されたが、ショートリコイル閉鎖方式を採用したこの機関銃の製造には当時最高の加工精度が要求される。この頃の当時の日本は軍艦とか大砲は大枚たはいていいものを買っていたが、工作機械に関しては全くといっていいほど関心がなく、外国でガタがきたのを安価で買っていた。工作機械での精度が甘いといいものが作れないのは当然の理で、しかも機関銃製造のノウハウがない当時の大日本帝国の工業力ではまともなマキシム機関銃が作れなかった。
製造されたマキシム機関銃は近衛師団に配備されたとされ、日清戦争の時期の日本陸軍は総数で200丁ほど保有していた。この200丁というのは要塞用から野戦用までひっくるめた数字だが、日清戦争では使われなかったという。資料によっては「使われた」とも書かれているが実際には良く分からない。ただ言えるのは使われたとされる資料でも「活躍した」という記載は一切ないし、受領した側でも故障が多いとして不評だった。
中世欧州において教会が「(強力な殺傷力を有する)弩は異教徒との戦いにおいてのみ用いて良い」と触れを出した様に、機関銃についても当初は「白人間の戦争には用いない」なる暗黙の規約があったとする説もあるが良く分からない。いずれにせよ弩はキリスト教徒間の戦闘にも躊躇なく用いられてきたし、それは「白人間の戦争」たる南北戦争やボーア戦争についても同じだったのである。
南アフリカ戦争は大英帝国の侵略戦争であり、ブール人がその被害者であった事からブール人に対して同情的な記述が多いが「現地アフリカ人からすればイギリス人もブール人も侵略者であった」事実は揺るがない。このことを押さえておかないと、彼らが白人の支配者として共同で統治することになる南アフリカ連邦とその後継である南アフリカ共和国において、黒人に対する差別と抑圧の典型であるアパルトヘイト政策がとられていくことを見逃すことになる。
大英帝国との戦争の最終局面の講和会議においてブール人は「アフリカ人には選挙権を与えないこと」を条件の一つとして主張。その結果1902年の講和条約において「アフリカ人の選挙権付与の問題は自治政体設置後に決定する」とされた。この事はアパルトヘイト政策の源流、すなわち「ブール人がアフリカ人の政治的進出を恐れていた事」を窺わせるのである。
一方、大英帝国がブール人の小さな国家二つを併合するのに2年半も要した事はその権威を大きく失墜させた。当時すでに工業力でアメリカ合衆国に抜かれており大英帝国の長い低迷の始まりとも見て取れる。戦争中の1901年1月にヴィクトリア女王が死去した事は大英帝国の転換を象徴していた。
この戦いには最終的に45万の兵員と2億3千万ポンドの戦費が費やされ、その巨大な財政赤字と膨大な国債が国家財政を破綻させた。そしてかかる状況下、自由党政権のもとでドイツの帝国主義的膨張に直面し「自由帝国主義」といわれる自由主義を維持しながらの帝国主義政策が展開される事になる。
こうした大英帝国の展開は、女性解放史に独特の足跡を残す事になった。英国保守党が「プリムローズ・リーグ」キャンペーンの成功によって保守派労働者や婦人層を支持層に取り込む事に成功した為、政権交代した自由党は革新政党にあるまじき事に労働者に(保守党の政策を継承する)帝国主義者的側面をアピールする一方で、女性参政権運動を武力で鎮圧する道を選ばざるを得なくなってしまったのである。
映画「未来を花束にして(Suffragette, 2015年)」フェミニズムを称揚する様に見せ掛けて保守派政党にも革新派政党にもダメージを与える典型的な「左の右」の手口…
それではネット上の第三世代フェミニストがどう反応したかというと「自分の身を守らねばならない人々に身の守り方を教えるのが私の仕事」と断言してサフラジェット運動家に柔術を指南した柔術家(演ヘレナ・ボナム・カーター)にのみ共感を示したのだった。ちゃんと、分かってらっしゃる…
日清戦争敗北をうけて、清朝内部で始まった康有為等の戊戌の変法はあくまで体制の上からの改革であり、一般民衆にはほとんど理解されていなかった。民衆はむしろ西洋の医療は幼児の目をくりぬいて薬を作っているとか、鉄道や汽船は怪異なものであり、電信柱があるから雨が降らないのだなどと信じ、またキリスト教徒が祖先の祭をしないことに伝統を壊すものという不快感を持ったものである。そのような反西洋文明、反キリスト教の運動を仇教運動といい、この様な民衆の排外的・反キリスト教感情を煽動して華北一帯に広まったのが義和団といわれる一種の宗教秘密結社であった。ここで忘れてはならないのは、その一方でむしろ逆に「列強による侵略に積極的に加担する方向」に勝機を見出した人々も存在したが彼らもまたその大半は同じくらい頑迷な迷信主義者に過ぎず、自分達の置かれている危機的状況を省みる事なく不毛な内ゲバに身を投じていったという現実である。似た様な構図ならインド大反乱(Indian Rebellion, 1857年~1858年)においても散見されるが、その黒幕は一向に蜂起しようとしない一般民衆に業を煮やして扇動に邁進したインド・インテリ階層であった。
まぁ「左の右」もこうしたタイプの「悪事」ならしばしば働くので、決して気を許すべきではないといえよう。
- この問題は「どうして日本においてだけ自力近代化が成功したか」と深く関わってくる。その主導層(明治維新元勲)は完璧には程遠いまでも「列強の侵略」に粉砕されも組み込まれもせずに済む道を何とか選取して独立を保ったし、彼らとそこまで分断されていなかった一般民衆層もまた相応の合理的判断に従って自らの指導者に従う道を選んだのである。そうして成立した大日本帝国は(独立後も諸勢力分断に苦しみ続けたイタリア王国やドイツ帝国と異なり)粛々と版籍奉還(1969年)、廃藩置県と藩債処分(1871年)、秩禄処分(1876年)を遂行して江戸幕藩体制をあっけなく解体し、フランス型郡県制に移行してしまう。白村江の戦い(663年)で敗戦し大陸から侵攻を受ける恐怖が高まると(既に問題が山積みとなっていた)伝統的氏姓制度をあっけなく放棄して律令国家に移行して以来の(1200年振り2回目の)手の平返し。そもそも日本の場合、戦国時代における一円領主化進行によって公家領や寺社領が押収され、貴族も寺社も事実上封建領主の立場を手放して俸禄や檀家からの御布施で生活する様になっていたので欧州でいう意味合いにおける革命遂行が必要となっていた事も幸いしたのかもしれない。
- この考え方の重要性は日清戦争勃発の主要因となった甲午農民戦争(Donghak Peasant Movement、Donghak Peasant Revolution、동학농민운동、동학농민혁명,1894年)にも見て取れる。その本質は祖国が列強から侵略される脅威に直面し、これを内部党争に活用する事しか思いつかない腐り果てた朝鮮王朝の中央両班達に業を煮やしての愛国農民達の蜂起であったが、現支配階層と協調しての祖国防衛戦線の樹立を目指した主流派に対し、その妥協に際して切り捨てられる事を恐れた奴隷民ら武闘派が講和を拒否して徹底抗戦を続けた結果、錯乱状態に陥った朝鮮王朝が大日本帝国軍と清朝軍に同時に鎮圧を要請する最悪の事態を招いてします。ちなみに農民軍の戦闘力を支えたのは、数多くの目撃談により日本より密かに横流しされた戊辰戦争当時の旧式銃とその実弾(興味深い事に後装銃を扱い慣れた前装銃に改造して使用)であったと目されている。水面下でどの様な動きがあった結果かは不明。
その一方でクルップ社は中国において陣営を問わず最新鋭の小銃や火器を売り込んで列強各国の顰蹙を買っていた。しかしまぁこの辺りは幕末日本で暗躍した外国人武器商の振る舞いと大差ない。
また東アジアにおいて義和団事変(1900年)が勃発すると大英帝国も北京への共同出兵に踏み切ったが、南アフリカ戦争の継続中であった為に兵力を割くことが出来ず、北京出兵の主力は大日本帝国軍と帝政ロシア軍にゆだねざるを得なかった。
帝政ロシア軍は事変後も満州占領から撤退しなかった。それで大英帝国はアジアにおける利権を守る為、それまでの外交の基本方針であった「光栄ある孤立」政策を改め、に日英同盟(1902年)を締結する。この同盟によって第日本帝国はコルダイト(無煙火薬)を大英帝国から大量に輸入する事が可能となった。
大日本帝国がマキシム機関銃の次に目をつけたのはフランスのホチキス社が発明したホチキス機関銃だった。次弾装填にガス圧を使う作動方式で、反動利用式のように微妙な調整を必要としないので当時の工業力でも作れると判断されたと推測される。日本では「保式機関砲」と呼ばれた。
明治31年(1898年)にフランスから2丁が輸入され日本陸軍での試験結果も良好。そのまま無断コピーという手もあったが、マキシム機関銃の失敗に懲りたのかフランスのホチキス社とライセンス契約を結んだ。ライセンス契約を結ぶと図面一式が手に入るし、組み立て方の手順書や検査方法も一式入手できる。なにより、作ってて分からないことがあればホチキス社に堂々と聞けたし、日本から技術者を派遣したりもできたのである。特に組み立て方や検査方法などは書面で分かりづらい一面もあり、大正・昭和になって恥もなく無断コピーしてもいいものが作れなかったのは、単純に図面がなかっただけではなく、こうしたものも入手できなかったからだろう。
ホチキス機関銃は当然日露戦争に投入された。配備数でいえば帝政ロシア軍より多かったぐらいだが、当時の野戦における機関銃の運用方法は手探りな部分が多く両軍ともその運用には苦労させられている。とはいえ当時の機関銃は3脚を入れれば50kg以上もあり、攻勢で機動運用するより防御で陣地に固定運用したほうがはるかに効率がいいというのは素人でも分かる話で、ロシア軍のマキシム機関銃は大いに活躍し、日本軍は大いに苦戦した。
日露戦争最初の激戦である南山の戦闘で日本軍は実に約4500人の死傷者を出した。当初「死傷者3000人」と大本営に打電され「零が1つ多いのではないか?」という確認の返信があったともいわれるぐらいに予想外の損害を被った日本は野戦での機関銃運用を諦めて配備している全ての機関銃を、旅順攻略部隊である第3軍に配備し、他の野戦軍には機関銃が一切配備されなかった。
しかし、野戦での機関銃の運用はやはり必要不可欠だった。当時の戦い方はまず野砲が戦いの火蓋を切りそして銃撃して隙をついて突撃するものである。野砲は榴散弾が主流。簡単にいえば砲弾にショットガンを内臓して敵目標直前で発射するようなものだったが当時の時限信管は火道式で後の機械信管と比べると遥かに精度が劣る。しかも敵との距離を見誤ると地面にもぐってから爆発してしまうし、兵員が散開してしまうと威力を発揮できなかった。そのために榴散弾の砲撃には涼しい顔をしていた古兵もいたというが、機関銃の射撃は受けた場合は伏せるしかなかったため、その威力は実際面よりも心理的な面で大きかった。日本軍とロシア軍では使用弾薬が違うために機関銃が射撃した場合、音でどちらが撃っているかはすぐに前線の兵士は理解できたので敵が機関銃を撃っているのにこちらの射撃音が聞こえないと露骨に士気が低下したといわれる。そのために「照準なんてどうでもいいからとにかく撃ってくれ!」と機関銃部隊に請願した前線指揮官もいたという。
重たすぎる機関銃は機動性に劣るので馬車の荷車に機関銃を載せたものも作られた。普通に考えてそういう目立つものが最前線で役に立たないのはわかりそうなものだが、日本・ロシア両軍で作られて戦場で使用された。言うまでもなく役に立たず両軍とも緒戦以降は使わなかった。
ところで日露戦争中、銃器類の生産を担当したのは東京砲兵工廠だった。当時の日本には明治12年()創設の東京砲兵工廠と大阪砲兵工廠の2大造兵廠があり、東京では銃器類、大阪では大砲類の生産を担当していた。重たい大砲の生産は大変だったが銃器類は本体(ライフルなどの銃器の完成品)自体が軽いせいもあり、弾薬も大砲の弾のように手作業での製作ではなく、当時からしてオートメーション設備があったので量産にも支障がなかった。日露戦争中、大砲の、特に榴弾の不足は深刻で鋼鉄製の砲弾の生産が追いつかず、鋳造で大砲の弾を作らせても需要に追いつかなかったのに、ライフル弾不足に直面しなかったのはここに理由があったのである。その為、東京砲兵工廠では戦争中でも余力があり、戦場で直面した銃器類の欠点などを改良する事ができた。クローズアップされるのはライフルで、日露戦争中の主力ライフルは30年式歩兵銃だったが、これを日露戦争中に改良を施し完成したのがあの傑作ライフルの38式歩兵銃だった。ホチキス機関銃も改良が行われ明治38年(1905年)に38年式機関銃として制式採用となった。
38年式機関銃は輸出も検討されたがホチキス社とのライセンス契約条項に「輸出していい」とは盛り込まれておらず、輸出しようとしたらホチキス社から文句がきた。この事が日本独自開発ともいえる3年式機関銃が作られるきっかけとなる。
そして…
欧州情勢は日露戦争以前の英・露仏・独墺伊(旧ハプスブルグ帝国メンバー)三勢力が鼎立していた状況から英仏露の三国協商と独墺伊の三国同盟の対立へと向かっていく。
- 露仏同盟(露Франко-русский союз、仏Alliance franco-russe、1894年1月4日)…1890年ドイツ帝国の宰相であったビスマルクが辞任するのにともない、従来のドイツ外交に変化がもたらされた。これまでのドイツ外交は、フランスの孤立化を重視する観点から対ロシア外交を重視したが、この年より親政を行う皇帝・ヴィルヘルム2世はこのことに固執しなかったので1887年より継続していた独露再保障条約が更新されない運びとなったのである。これを契機としてフランスとロシアの交渉が1891年から公然化。経済的対立をふくむ欧州情勢の混迷を背景に三国同盟(1882年~1915年、ドイツ帝国,オーストリア=ハンガリー二重帝国、イタリア王国)を仮想敵とする集団的自衛権を定めた軍事同盟が成立。
- 英仏協商(Entente Cordiale、1904年4月8日)…イギリスとフランスの間で調印された外交文書、およびそれによる英仏間の外交関係。原語の意味は「友好的な相互理解」を意味する。これにより両国の植民地政策の対立は解消され、中世の百年戦争以来数百年に渡る英仏間の対立関係に終止符が打たれた。
- 英露協商(英Anglo-Russian Entente、露Англо-русское соглашение、1907年)…日露戦争を終らせたポーツマス条約によって極東の勢力圏が確定した事を受け、イラン、アフガニスタン、チベットにおける大英帝国と帝政ロシアの勢力範囲を決定。これによりイギリスとロシアの対立関係が解消した。
大英帝国は日露戦争に勝利した日本への評価を改め、それまでの日英同盟を攻守同盟に強化した(第二回日英同盟協約、1905年8月12日)。ロシアの南下政策への警戒態勢を流用して山東半島におけるドイツ租借地の孤立を目論んだのである。そして…
- 日露協約(1907年〜1916年)…日露戦争後に締結された大日本帝国と帝政ロシアがお互いに権益を認め合った4次に亘る協約。1907年7月30日に第1次条約が調印され、1916年7月3日に第4次条約が調印された。秘密条項では日本はロシアの外モンゴルにおける権益、ロシアは日本の朝鮮における権益を認めた。
- 日仏協約(1907年6月10日~1941年の日本軍による仏印進駐)…パリで駐仏日本大使栗野慎一郎とフランス外相ステファン・ピションの間で調印。フランスが日本との関係を相互的最恵国待遇に引き上げる事に同意する代わりに日本はフランスのインドシナ半島支配を容認しベトナム人留学生による日本を拠点とした独立運動(ドンズー運動)を取り締まることを約束した。また清の独立を保全するとともに清国内におけるお互いの勢力圏を認め合った。これによりフランスは広東・広西・雲南を、日本は満州と蒙古、それに秘密協定によって福建を自国の勢力圏として相手国側に承認させている。なお、フランス側が議会・世論対策のために自国マスコミに交渉内容をリークした為に清国側からの抗議を受ける事態も生じた。
かくして大英帝国は仮想敵国を日露戦争の敗北により国力が疲弊したロシアからドイツに切り替え、ドイツはイギリスとの建艦競争を拡大していくのである。さらには…
- 「未回収のイタリア」と呼ばれる南ティロル・トリエステなどを巡りオーストリアとの領土問題を抱えていたイタリアは1902年に仏伊協商をフランスと結び、ドイツがフランスを攻撃する際にはイタリアは参加しないことを約束。以降もイタリアは三国協商側への接近を続け、1915年4月イギリスとの間にロンドン秘密条約を秘密裏に結んで未回収のイタリアをイタリアに割譲する算段をとりつけた。同年5月には連合国側に付いてオーストリアに宣戦し、三国同盟は二国同盟に。
- 一方、同盟側は青年トルコ人革命(1908年)を契機に始まった第二次立憲制期(1908年~1919年)オスマン帝国を味方に引き込む事に成功する。
この間の化学工業の発展を受けて1906年フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュがドイツでアンモニアを大量生産して窒素化合物をつくるハーバー・ボッシュ法を発見。1913年に褐炭から肥料を生産する体制が整って各国の人口増大を支える食料増産が約束されて、総力戦を戦う準備が整った訳である。
一方、こうした国際展開に翻弄されたのが中国大陸でした。
辛亥革命当時の記録に「支那内乱独逸本腰にて北京軍を援助、我日本は半腰的遠慮勝の弱腰にて革命軍への効を奏し」「公然事明かせば独逸と日本の尻押戦争の感あり」と記された様に20世紀に入ると大日本帝国とドイツ帝国が中国本土を舞台に熾烈な武器販売合戦を繰り広げる様にある。大日本帝国におけるそうした動きの嚆矢は日清・日露戦争を通じてその生産規模を飛躍的に伸ばしてきた東京砲兵工廠と大阪砲兵工廠の生産力を維持する為に明治41年(1908年)に中国武器市場への輸出を担う秦平組合が設立された。
- 明治44年(1911年)に辛亥革命が勃発すると清朝政府は在清公使館付武官青木宣純経由で砲弾約30万発、小銃弾6,400万発、小銃1万6千丁を購入。契約成立日より3週間以内に1/3、残り2/3も4週間以内に清国陸軍に納品する条件を日本側は満たしたが(総額約273万円)、清朝側は3分割支払いの1回目分しか支払わず、残りは中華民国政府に引き継がれた。また陸軍省はこれと別途に奉天軍機閔局向けに三十年式小銃実弾500万発、三十八年式弾底信管4,500発、三十一年式速射砲榴弾炸薬4,500発、さらに秦平組合でなく大林組経由で戦利露軍小銃37,480挺、同実弾3,260万発を払い下げている。
- その一方で(田中義一軍務局長など)参謀部が原敬宰相に働きかける形で革命軍にも武器供給が行われたが、小銃7万1,400挺~6万8,000挺、同実弾34,000万発~28,000万発、機関銃6門、山砲6門、同実弾5,000万発説や、村田銃や戦利露軍小銃といった旧式銃2万2,000挺、同実弾2,000万発説などいずれも検証が十分ではない。いずれにせよ革命軍側に支払い能力がなかった事から借款の形をとり、上掲の清朝政府未払い分と合わせ対華21ヶ条要求(1915年)の基底を為す形となったのである。
ここで恐ろしいのが、かかる東アジア近代史のあらゆる場面に顔を出す「妖怪」袁世凱(1859年~1916年)の怪物的暗躍…
- 李鴻章幕下の淮軍で頭角を現し、武弁として朝鮮半島に赴任すると外交顧問として馬建常(元神戸・大阪領事)とメレンドルフを迎え入れ事実上の国王として君臨。国内に常駐する大日本帝国への挑発を繰り返して日清戦争勃発を招き国外逃亡を余儀なくされる。
- 山東地方に割拠する宗教結社に過ぎなかった義和団を追放して北京に向かわせ、義和団の乱を勃発させる。
- 政争を巧みに制して辛亥革命によって樹立された中華民国を乗っ取ると皇帝に即位。しかしながらその栄華は長くは続かず、退位して逃亡中に死亡。
- 実は皇帝即位には第一次世界大戦(1914年~1918年)泥沼化の影響を受けて列強が投資を引き上げ、その結果中華民国が経済的困難に陥って求心力を低下させた事への対応策という側面もあったらしい。そして袁世凱没後の軍閥割拠期に経済的援助を引き継いだのが西原借款だったという次第…
それよりさらに恐ろしかったのが「中国進出後進国」たる米国から渡ってきたウィルソン大統領の提唱したいわゆる「ウィルソン主義」信者達の朝鮮半島「三一万歳事件(1919年3月1日)」や中国「五四運動(1919年5月4日)」の裏側における暗躍。「東アジア政局のリセット」を画策しての動きだったが1919年10月2日ウィルソン大統領が脳梗塞を発症して政務遂行が不可能となって大統領夫人のイーディス・ウィルソン(ポカホンタスの末裔)が事実上の「米国初の女性大統領」として執務を代行する様になるとあっけなく切り捨てられ、活動の終焉を迎えてしまう。
ちなみに中国共産党はかかる活動に動員された中国人運動家集団を母体に発足したと目されている。何の事はない。(軍事面および資金面でパキスタン軍の諜報機関であるISI(軍統合情報局)を通してCIAの支援を受けていた)タリバン同様、中国共産党もまた「アメリカの工作が残した置き土産」の一つだったという次第なのである。
こうして1910年代には、その長過ぎる歴史故に「(国家維持に必要な火力と機動力を装備した常備軍を法実証主義に立脚する中央集権的官僚体制が徴税によって賄う)主権国家」への移行を拒み続けてきた「中華王朝(紀元前221年~)末裔としての清朝(1616年~1912年)」「神聖ローマ帝国(800年/962年~1806年)継承国としてのハプスブルグ君主国(1804年~1919年)」「オスマン帝国(1299年~1922年)」「帝政ロシア(1613年/1721年~1917年)」が揃って地図上から消え、国家間競争が全てとなる総力戦態勢時代(1910年代~1970年代)が始まります。それは第一次世界大戦(1914年~1918年)で被った痛手により経済的に没落した欧州文化圏が元の経済水準に戻るまでの復興期でもあったとされています。一方、こうやって全体像を俯瞰すると「主権国家への移行が総力戦遂行と不可分な形で進行した」英国、米国、ドイツ、日本と「必ずしもそうとはいえなかった」フランスやイタリアの戦争遂行能力に大きな差がある現実も浮かび上がってくるという次第(実際、フランスは軍事大国でありながらしばしば英国やドイツに敗戦し、総力戦遂行と無関係に台頭したイタリアン・ファシズムは世界恐慌に直面した時適切に対応する事が出来なかったし、戦うと弱かった)。
技術発展史を軽視する伝統的反帝国主義史観から脱する為(そう、マルクスらの予測と異なり技術の発展は必然的にプロレタリアート革命や民族独立運動に直接結びついた訳ではなかったのである!!)、文面自体はあちこちいじってあります。