ノルマンディー公リシャール1世の娘エンマ(Emma of Normandy、 985年頃〜1052年)
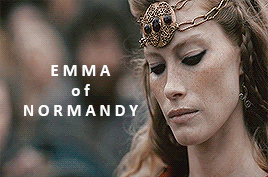
「ノルマンの宝石」と呼ばれるほどの美女で、イングランド王エゼルレッド2世(在位978年〜1013年,1014年〜1016年)の未亡人として北海三国王クヌート大王(イングランド王1016年〜1035年、デンマーク王1018年〜1035年、ノルウェー王1028年/1030年〜1035年)と結婚。アングロサクソン朝の王統にノルマン公の血を混ぜた事でノルマン・コンクエスト(1066年)の遠因を生む。
2人の夫ともうけた子供たちのうち、それぞれから1人ずつが後にイングランド王になった。すなわちクヌートとの子ハーデクヌーズと、エゼルレッド2世との子エドワード懺悔王である。
1035年クヌートが亡くなるとデンマーク王は約束通りハーデクヌーズが継承したが、イングランド王の王冠をかぶったのは、イングランド貴族の支持を受けた、ハーデクヌーズの異母兄ハロルドだった。
1036年息子のエドワードとアルフレッドがデンマークのエマに会うために、亡命先のノルマンディーから帰国した。ハロルドに対抗する動きのように思われる。しかし、弟のアルフレッドは捕らえられ、目を潰され、その傷がもとでまもなく死んでしまった。兄のエドワードはノルマンディーに逃げ帰った。エマ本人もすぐさまブルッヘ、それからフランドル伯の宮廷に逃げた。「エマ賛辞(Encomium Emmae)」という本はその宮廷で書かれたものである。
1040年ハロルドが亡くなり、ハーデクヌーズがイングランド王の王冠をかぶった。ハーデクヌーズはノルウェーとスウェーデンの領土を失っていたが、デンマークのそれは確保していた。
1041年エドワードが帰国。ハーデクヌーズはノルマンディー宮廷に対して、もし自分に子供がいなければエドワードが王になるべきだと言った。
1042年ハーデクヌーズが亡くなって、エドワードがイングランド王になったが、その時息子のエドワードでなくマグヌスを支持したので、ずっと見捨てられたままだった。
評価
2度の結婚の2度とも最初の妻より劣っていると見られることが多い。どちらものウィットビー教会会議(664年)の後、正式にケルト系キリスト教から脱っしてローマ・カトリック教会の傘下に移り、アングロサクソン文化、ケルト文化、ピクト文化、ビザンティン文化の美術要素を統合したブリテン島美術の中心地として重要な役割を演じた七王国時代(Heptarchy=ヘプターキー、西ローマ皇帝ホノリウスがブリタンニアを放棄した409年(End of Roman rule in Britain)~ウェセックス王のエグバートがエランダンの戦い(Battle of Ellendun)によってカレドニアを除くブリテン島を統一した825年)のアングル人王朝ノーサンブリア王国(653年~954年)の出身者であったが、この国自体は9世紀よりヴァイキング活動(北方諸族の略奪遠征)を活発化させたデーン人に併合されている。
- 出産中の合併症から亡くなったエゼルレッド2世の最初の妻エルフギフ・オブ・ヨークは多くの人々から尊敬されていた。ノーサンブリア伯トレド(Thored)の娘である。
- クヌートとの結婚では、先に「仮祝言した」妻エルギフ・オブ・ノーサンプトンの影に隠れ当時はエルギフ・オブ・ノーマンディーという名で呼ばれていた。ちなみにエルギフ・オブ・ノーサンプトンは南部ノーサンブリアの伯爵アーセルムの娘である。
ともあれ、エマの2度の結婚はイングランドとノルマンディーの強い絆を生み、後にそれはエマの大甥ウィリアム1世による1066年のノルマン・コンクエストで頂点を迎えることになる。
欧州史の主役がデーン人からノルマン人に推移していく時代の一幕…
欧州における「言語ナショナリズム」の源流。
ケルト語圏で修道院文化の生み出したものの中で、美術面に劣らず重要なのは俗語(ヴァーナキュラー)文学の誕生だろう。
たとえばフランス語の最初の文学は11世紀末の武勲詩「ローランの歌(1098年頃)」であり、ドイツ語の国民的叙事詩「ニーベルンゲンの歌」は13世紀となる。英語についてはやや早く、古英語(アングロサクソン語)の英雄伝「ベオウルフ」は8世紀初頭に成立したとされる。
ヒベルニア(アイルランド)のエール(ゲール)語についてみると、現存する最古の文書こそ「ナ・ヌイドレ(ドゥンコウ)書(1106年頃)」「ラグネッヘ(レンスター)書(1160年頃)」など12世紀となるが、その起源をたどると6世紀まで行き着く。もっとも有名なのは6世紀のダラーン・フォルギルによる「コルムキル(聖コルンバ)頌歌」である。ワリア(ウェールズ)のカムリー語の場合も現存文書は13世紀以降のものだが「アネイリンの書」「タリエシンの書」などのカムリー語詩歌の創作年代が、その歴史状況からみて6世紀にまでさかのぼることは、研究者間のほぼ一致した見解である。
西欧の主要言語における文学の成立が11世紀~12世紀以降になり、もっとも早い英語でもせいぜい8世紀なのに、ゲール語やカムリー語などどうひいき目にみてもメジャーとはいえない言語において、6世紀という早い段階で書きことばによる文学がなぜ誕生したか。
この答えはまさにその文化的周縁性にあるといっていいだろう。フランスの社会言語学者バッジオーニの提唱していることだが、ローマ帝国の周縁部(リメース)とその隣接地帯、すなわちブリタニア諸島、ドイツ北東部、スカンジナビア、ボヘミアなどではラテン語は教養人にとっても外国語でしかなく、その使われ方も古風なままであった。権威ある言語が自由に日常的に用いられないというなかで、地元のことばをそれに代用するという考え方が生まれ、ラテン語に似せた書きことばでの使用がはじまったというわけである。
したがってヨーロッパでは、ローマ帝国周縁部の内外で最初に、日常的に用いられる俗語による書きことばが誕生した。こうした俗語が現代の国語・民族語の形成につながる。ブリタニア諸島での言語についてみれば、ローマ帝国のはっきりとした外部であるヒベルニア(アイルランド)では、6世紀には詩歌ばかりでなく、年代記や法的文書までゲール語で書かれるようになった。
カムリー語の法的文書は10世紀、聖人伝はラテン語からの翻訳で11世紀末になって登場するので、ゲール語と比べるとその使用頻度は低い。ワリア(ウェールズ)が、その少なくとも一部はローマ帝国領内だった事とも関係してくるだろう。
スカンジナビアでは、ローマ帝国がまだ活力を保っていた後二世紀にルーン(ルーネ)文字が誕生し、北ドイツでは4世紀にウルフィラなる僧侶によって、ゴート文字を用いるゴート語新約聖書の翻訳が試みられた。文字の作成は文学の誕生以前の独自の書記文化創出であり、まさにローマ帝国周縁部での言語的権威創出の試みということができる。
この点ではケルト語のオガム文字もそうした試みの一つだといえるが、3世紀末~8世紀の墓碑銘などの碑文に用いられたにすぎなかった。その意味ではこちらは失敗事例といったほうがいい。
これに対して、ラテン語が教養人のことばとしてふつうに用いられた地中海地域では、いつまでもラテン語の書きことばとしての権威が失われず、地元の言語の文字使用が結果として遅れた。さらにいえば、ローマ帝国期の俗ラテン語期を経て、古典ラテン語の権威が9世紀には確立し、16世紀という近代はじめにまで持続したフランスでは、国家を超えるその権威をフランス語が引き継ごうとした。そこでフランス語のヨーロッパ全域にわたる普遍性が、まさにラテン語の生まれ変わりとしてとして主張されることになる。
*「想像の共同体: ナショナリズムの起源と流行(Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983年)」の著者ベネディクト・アンダーソンは「想像の共同体としてのクレオール共同体」に興味を寄せている。それは英語ないしはスペイン語という共通言語がありながら、ヨーロッパのどの地域よりも早くに「国民」という観念を成り立たせていたからだった(クレオール・ナショナリズム)。これは上掲の様な「周縁性」の産物と考えるべきだろう。そういえば欧州の中世前期、特にロマネズク文化を牽引したのは「周縁部」の数珠繋ぎに成功したノルマン人ではなかったか。
イングランドにおける古英語の残存
7世紀には「七王国」のマーシア、エセックス、ウェセックスなどでも、エイダンの弟子筋によってヒベルニア系キリスト教の布教が進み、ヒベルニア(アイルランド)、アルバ(スコットランド)、ワリア(ウェールズ)ばかりでなく、イングランドでも優勢になる。ただしキリスト教は絶対的権威を獲得しておらず、首領レベルでもこの当時は異教の残存がみられた。それは7世紀におけるアングロサクソン人の文字導入にまで影響を及ぼした。
大陸に分立建国したゲルマン諸族もこの頃法的文書が誕生していたが、それはラテン語によっていた。ところが、七王国のアングロサクソン人においては古英語だったのである。口伝の慣習法はすべてアングロサクソン語であり、この成文化という側面はあったが、ラテン語が絶対的権威を保持していなかったので、こうしたことが可能になったことは、大陸との比較において明白である。この場合も、周縁的文化地域での、俗語という新たな形での書きことばの誕生ということができる。
*こうしたケルト文化の複雑怪奇な展開はイベリア半島にも大きな爪痕を残している。
まさかの「(「ハダル化したバトウ」としての) ローマ人によるラテン語文学創設」の精神的継承者は(やはり「ハダル化したバトウ」という側面も有する)ケルト人(特にイングランド、ウェールズ、フランスのブルターニュ地方、イベリア半島のガリシア地方に割拠したブルトン人)だったという話…
とりあえず、以下続報…