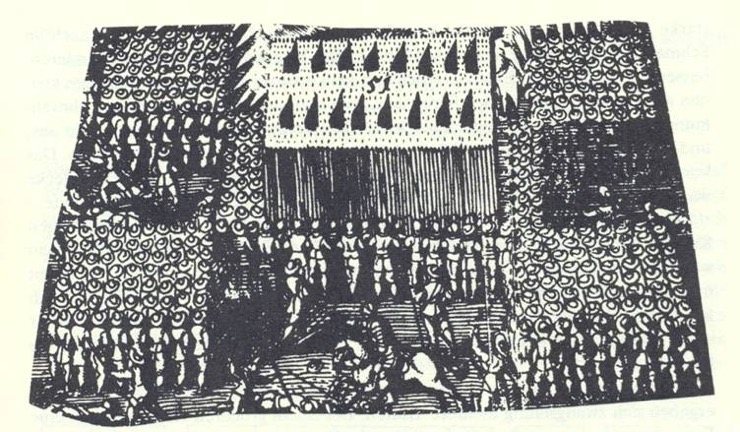火砲や冒険商船の発達が「(十分な火力と機動量を有する常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって養う)主権国家(Civitas Sui Iuris)体制」を準備したのは歴史的事実。
主権国家体制(Civitas Sui Iuris) - Wikipedia
16世紀から18世紀にかけての欧州において形成された国家のあり方と世界秩序。中世における普遍的世界の崩壊の産物。各国の個別性および領域支配を前提とし、それぞれがローマ教皇や神聖ローマ皇帝ではなく、君主ないし共和国の主権が最高で絶対な存在とされた。
英仏間で戦われた百年戦争およびドイツを舞台に繰り広げられた三十年戦争を通じて形成され、両戦争によって近代国家のかたちが整えられていった。これが1、2箇所で出現するのではなく、諸国家のシステムとしてヨーロッパ全域で成立した点が重要である。
18世紀 - 19世紀を通じて世界的に拡大し、現代も基本的には踏襲されている世界政治システムである。
しかしながら「常備軍に立脚した国家」は、少なくともその登場当初においては何も欧州の専売特許という訳でもなかったのでした。

何しろ出発点はイスラム世界を代表する14世紀の歴史家イブン・ハルドゥーン(Ibn Khaldūn、1332年〜1406年)が「歴史序説(al‐Muqaddima)」や「イバルの書(Kitāb al‐‘ibar)」の中で語った「田舎(バトウ)が都心(ハダル)を打倒し続ける循環王朝史観」という次第。
- 古代オリエント世界を最初に統一したのは、メソポタミア文明の外れに起ったアケメネス朝ペルシャ(紀元前550年~紀元前330年)だった。この時滅ぼされた都市国家群の祭政一致体制(神殿宗教)から「啓典の民(ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒)」が誕生する。
- 古代ギリシャ世界を史上初めて統一したのはギリシャ文明圏の外れに存在するマケドニア王国(紀元前808年〜紀元前168年)だった。彼らがアケメネス朝ペルシャを滅ぼし、かつ自らも内紛で滅んだ事によってヘレニズム文明圏が成立する。
- 古代地中海世界を統一したのはイタリア半島におけるギリシャ植民地とエトルリア文明圏のさらに外れに起ったローマ人国家(紀元前753年〜1453年)だった。
- そして曲がりなりにもイスラム文化圏の一員として地中海世界を再統一したのは中央アジアよりアナトリア半島に進出したテュルク系部族の末裔が築いたオスマン帝国(1299年〜1922年)だった。
- 古代中華世界を最初に統一したのは、西の外れに起った秦(紀元前778年〜紀元前206年)だった。以降も中華文明圏は清代(1616年〜1912年)まで「田舎(バトウ)が都心(ハダル)を打倒し続ける循環王朝史観」を忠実に繰り返し続ける。
というよりむしろ「(十分な火力と機動量を有する常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって養う)主権国家(Civitas Sui Iuris)体制」はこうした循環王朝史観を超克する為に現れたものと考えるべきであり、それに向けての要求水準が欧州より高かった地域なら他にいくらでもあったのです。
それでは実際に「(十分な火力を備えた)常備軍」が勝利を飾っていく歴史に目を向けて見ましょう。
新式スペイン軍の編成
レコンキスタを完遂しイベリア半島の過半を支配下に置く様になったスペイン王国は,1494年におけるフランスのイタリア半島侵攻を契機にイタリア戦争が勃発するとアラゴン王国による継承権を理由にこの戦争に介入。しかしゴンサロ・フェルナンデス・デ・コルドバを総司令官するスペイン軍はセミナラの戦いでフランス重騎兵とスイス傭兵を主力とするフランス軍に敗北してしまう。
当時のスペイン軍は山岳地域でのゲリラ戦に特化し、剣と円盾を装備した歩兵と、ヒネーテ(Jinete)と呼ばれる軽騎兵を中心としていたが、これを契機に円盾と剣を廃止し、スイス槍兵同様にパイクを持たせた。さらに槍兵に密集隊形(方陣)を組ませ、周囲と両翼に袖のように投射兵(クロスボウ、銃)を配置。さらに士官の数を増加させ、それまでたった1人の士官が兵士100人から600人を指揮していた状況を兵士300人につき4人から6人の士官が付く様に改善して部隊運用性を高めている。
新式スペイン軍VSフランス騎兵&スイス槍歩兵「チェリニョーラの戦い(Battle of Cerignola、1503年4月21日)」
正規軍同士の戦争で火力が重装騎兵を破った史上初めての戦い。スペイン軍の兵力は諸説あるが、騎兵1600名、歩兵6000名程度で丘の上に陣を取り、周囲を塹壕と土塁で補強していた。他に500名前後のアルケブス(火縄銃)を装備したドイツ人傭兵がおり、この部隊はマクシミリアン1世が派遣した援軍であった。砲は13門。これに対しフランス軍は、騎兵650名、歩兵7000名、砲26門。銃兵も存在はしていたが歩兵の主力はスイス槍兵だった。
フランス軍は前日の軽騎兵による妨害で十分な偵察ができず、塹壕の存在を察知出来ず、まずこれが最初の禍根となる。
最初に動いたのはフランス軍の騎兵。スペイン側は騎兵が塹壕で停止したところを大砲の斉射によって混乱させようとしたが、突如としてスペイン軍の火薬庫の一つが爆発。驚いた砲兵が予定より早く斉射を行ってしまった事から失敗に終わる。
代わりに力を発揮したのがドイツ傭兵で、塹壕で停止した騎兵を火力で射すくめて指揮官を戦死させている。フランス軍は次いで歩兵を前進させ、塹壕を突破せんとスイス槍兵に3度にわたって突撃を仕掛けさせたが全て撃退されスイス槍兵の指揮官も戦死。あまりの損害の多さに撤退を開始したフランス軍をスペイン軍は直ちに追撃。フランスの遺棄していった大砲を全て鹵獲した。
この戦いによるフランス軍の損害が3000名を超えた一方のスペイン軍の損害は100名前後に過ぎず、スペイン軍はフランス軍をナポリから追い出してその全土を制圧。1504年、戦力を再編できぬフランス軍はイタリアから撤退し、第二次イタリア戦争は終結したのである。
オスマン帝国のイェニチェリ歩兵隊VSイラン騎兵「チャルディラーンの戦い(Battle of Chaldiran、Chaldoran あるいはÇaldıranとも。1514年8月23日)」
6万から20万の大軍を擁するオスマン帝国軍と、それまで宗教的情熱を武器に無敵を誇ってきたサファヴィー朝軍のクズルバシュ(サファヴィー教団に深く帰依するトルコ系部族長に指揮される騎馬軍団)4万が衝突した戦いである。
夜明けとともにクズルバシュの怒濤の様な猛攻が始まり、オスマン帝国軍右翼を守るアナトリア騎兵軍を突き崩しかけたが、やがてイェニチェリと鎖でつないだ大砲を軍勢の中央に配置したオスマン帝国軍が騎兵をことごとく撃ち倒しててッ劣勢を挽回。右翼も救援に回ったイェニチェリ鉄砲隊の活躍で形勢逆転。9月にはタブリーズを占領する戦果を上げたが、補給の困難と遠征による疲れや軍勢内部に徐々に広がった厭戦気分から深追いをさけて退却せざるを得なくなった。
以降はサファヴィー朝もマムルーク(奴隷戦士)の近衛兵団とイラン系砲兵を主力とする様になりクズルバシュは失脚を余儀なくされる。
オスマン帝国のイェニチェリ歩兵隊VSエジプトのマルムーク騎兵「マルジュ・ダービクの戦い(Ma'rakat Marj Dābiq、1516年)」
エジプトのマムルーク朝は15世紀に入ると政治腐敗、アミール同士の絶え間ない内紛、疫病(ペスト)の流行による人口の減少とそれにともなう農業・手工業の衰退、イタリア商人の進出とポルトガル勢力のインド洋への出現による東西交易の停滞などによって深刻な打撃を受けた。それで16世紀初頭には250年続いたマムルーク体制は激しく動揺していた。
その結果、1517年にマムルーク朝はオスマン帝国によってあっけなく滅ぼされ、エジプト州として帝国に編入されることになる。
オスマン帝国もマムルークと同じように君主に絶対の忠誠を誓う子飼いの軍隊であるカプクルを抱えていたが、その主力であるイェニチェリが銃火器で武装した歩兵であり、マムルーク朝の崩壊は旧来からの弓を武器とする騎兵であったマムルークの軍事的な限界を示す事件ともなったのである。
ティムール朝残党VSインド地侍「第一次パーニーパットの戦い(The First Battle of Panipat、1526年4月21日)」
戦象1,000頭を含む100,000人以上の大群を擁する北インドの覇者ローディー朝が、動員数こそ12,000人程度だったが鉄砲や大砲を有効にバーブルの軍勢に敗れムガル朝創始につながった。
インダス川を渡河したバーブルは自軍の一部を民家の多いパーニーパットに置く一方、木の枝で覆い隠した壕で自軍を保護し、実数が悟られないように隠蔽。また自軍の前面に多数の荷車を縛り付けて並べた「防壁」をつくり、荷車の間ごとについたてを作って鉄砲や大砲を発砲できるようにした。
実戦ではローディー軍がバーブル軍の布陣の固さに攻めあぐねて躊躇した隙を突いて側面と背後から攻撃。これに連動する形で前面から鉄砲や大砲の連続射撃で16,000人以上を殺したという。
日本における戦国大名連合軍同士の決戦「長篠の戦い(1575年)」
三河国長篠城(現愛知県新城市長篠)をめぐり、織田信長・徳川家康連合軍3万8000と武田勝頼軍1万5000が衝突。
信長軍は一説に拠れば3000丁もの火縄銃を用意し、野戦築城によって「三段構えの陣」を構築した上で武田側の後背地たる鳶ヶ巣山を奇襲で占拠し無謀な突撃以外の選択肢を封じて圧勝した。
ここで見られる野戦築城(より具体的には塹壕線)による敵部隊の突撃阻止と、火砲の集中投入による殲滅の組み合わせは、宣教師の口づてで織田信長の耳に伝わった「チェリニョーラの戦い(1503年)」などから考案されたともいわれている。
「テルシオ(Tercio、スペイン方陣)」と「オランダ式大隊(Dutch battalion)」
スペイン軍はさらにパイクと小銃を組み合わせた先陣を工夫して「パドヴァの戦い(1525年)」においてフランス軍を分断し総崩れに追い込んだ。
そしてこれ以降スペインはフランス同様に「常備軍問題」を抱える事になり、多大な軍事費出費を余儀なくされる事となる。その多くは新大陸から掠奪してきた金銀で賄われ、ハイパーインフレを引き起こす事に。その軍事的優位は16世紀末まで続いたが、17世紀に入るとネーデルラントのマウリッツ・ファン・ナッサウがテルシオを破る新式軍隊を編成し、事前訓練の徹底による柔軟な機動力を武器とする「オランダ式大隊(Dutch battalion)」を編み出す。
その軍事改革は兵士を供給したザクセン選帝侯国経由で北欧に伝わりスウェーデンのグスタフ2世アドルフがさらに研鑽して「ブライテンフェルトの戦い(1631年)」における神聖ローマ皇帝軍のスペイン方陣に対する勝利を現出させる事になる。
オラニエ公マウリッツ・ファン・ナッサウ(Maurits van Nassau, 1567年〜1625年)
スペインからの独立戦争(八十年戦争)を始めたオランダ総督オラニエ公ウィレム1世の次男で、フィリップス・ウィレムの弟、フレデリック・ヘンドリックの兄。父の死後、戦争において中心的な役割を果たした。死に臨んで「2プラス2は4である」ということを自己の信条にしたほどの合理主義者で、自らの軍隊に徹底した訓練を行うと共にそのマニュアル化を行った。これがヨーロッパ各国の軍隊に多大な影響を与えたことから「軍事革命」とも評価される。
1567年にドイツ西部のディレンブルクで生まれた。父はウィレム1世、母アンナはザクセン選帝侯モーリッツの娘。母方の祖父の名を取ってマウリッツ(モーリッツ)と命名され、父方の叔父のナッサウ=ディレンブルク伯ヨハン6世の元で育てられた。
1584年に父の暗殺後、1585年にホラント州とゼーラント州の総督となった。当初はイングランドから派遣されたレスター伯ロバート・ダドリーがオランダを率いていたが、指導力不足から1587年にイングランドに帰国するとマウリッツがオランダを率いる立場に置かれ、1590年にユトレヒト州・ヘルダーラント州・オーファーアイセル州総督も兼ねるようになる。
戦争はスペイン領ネーデルラント総督のパルマ公アレッサンドロ・ファルネーゼがオランダの都市を奪い続けていたが、1588年のアルマダの海戦でスペインが敗北、翌1589年にスペイン王フェリペ2世がフランスの内戦(ユグノー戦争)に介入してパルマ公をフランスへ出兵させたため、その隙に都市奪還を図り1590年にブレダ、1591年にデーフェンター、ズトフェン、ナイメーヘンを、1592年にスティーンワイカーラント、1593年にヘールトラウデンベルフを奪還してオーファーアイセル州・ヘルダーラント州・北ブラバント州を回復、1594年にはフローニンゲン州も取り戻してオランダの領土を拡大、1597年までに再び北部7州をまとめ上げた。1596年にはイングランド・フランスとグリニッジ条約を締結、2国からオランダの承認・対スペイン同盟締結でオランダの地位を固めた。
教養人でもあった為に古代ローマ帝国時代の軍事に関する文献を踏まえつつ、自らの軍隊に独自の教練を施して軍の強化に成功し、1597年のトゥルンハウトの戦い、1600年のニーウポールトの戦いで勝利を重ね、八十年戦争を優勢に進めた。
しかし1603年から参戦したスペインの将軍アンブロジオ・スピノラが南部の都市を奪還して回り、1604年にグリニッジ同盟が解散、スペインが国家破産を宣言するなど深刻な財政難に陥っていたスペイン・オランダ両国は次第に戦争を継続することが困難になり、1608年よりハーグで和平交渉が行われ、最終的には1609年にアントウェルペンで12年間の休戦協定が成立した。
戦時中の1602年にオランダ東インド会社が設立されてオランダ人がアジアに進出、毛織物貿易が盛んに行われ、オランダは黄金時代を迎えることとなる(オランダ海上帝国)。一方で、父が暗殺されたようにオランダ内部では絶えず政争が続いていて、休戦協定はホラント州法律顧問のヨーハン・ファン・オルデンバルネフェルトが商人層を代表して結んだが、庶民派とマウリッツは協定に不満で両者は対立関係となった。
宗教問題でもカルヴァン主義の予定説をどう解釈すべきかが政治問題に発展、オルデンバルネフェルトは予定説を柔軟に解釈すべきとする寛容派に属したが、マウリッツは厳格に解釈しようとする厳格派に肩入れした。1618年に開かれたドルトレヒト会議で厳格派が主流となり、ドルト信仰基準が採択され、1619年にオルデンバルネフェルトを処刑して自らの政権を維持した。
1621年に停戦が終わるとスピノラと再戦、1624年にスペイン軍に包囲されたブレダを救援しようとしたが、翌1625年、決着が着く前にハーグで57歳で死去。
生涯独身を通し嫡子がなかったため、家督と地位は異母弟のフレデリック・ヘンドリックに受け継がれたが庶子にウィレム、ローデウェイクがおり、ローデウェイクの息子である孫ヘンドリックはオランダ侵略戦争、大同盟戦争、スペイン継承戦争で従軍してアウウェルケルク卿と名乗り、この家系はナッサウ=アウウェルケルク家として続いた。
マウリッツの軍事革命
従兄のナッサウ=ジーゲン伯ヨハン7世(叔父ヨハン6世の子)と共に行った一連の軍事訓練は、「軍事革命」とも評価される画期的なものであった。もちろん、従来の軍隊にも軍事訓練はあったが、マウリッツはその訓練を非常に精緻なものとした。
例えば、銃を扱う際にもその動作を数十にまで細分化し、かけ声に合わせて一斉に動作できるようにした。また、行進の規則を定めることで、指令に従って軍団が迅速に陣形を変えることを可能にした。こうした訓練は、非戦闘中の兵士の士気を維持させることにもなった。
また訓練を通じて、元来は傭兵の寄せ集めでしかなかった軍隊の中に、ある種の連帯意識を形成させることにも寄与した。しかもこれらの訓練マニュアルは秘密裏にされず、書物として刊行された(『武器の操作、火縄銃・マスケット銃・槍について、オラニエ公マウリッツ閣下の命令によって著す』、日本語未訳)。そのため、諸外国がマウリッツの基本教練を参考にして、自国の軍隊を鍛え上げるようになった。
さらにマウリッツは、パイク兵の方陣(テルシオ)による白兵戦が主流であった当時のヨーロッパの陸戦を刷新し、歩兵・騎兵に砲兵を加えた三兵戦術の基盤を築いた。
マウリッツが生きている間は、それでも名将スピノラ率いるスペイン軍との戦闘は五分五分といったところであったが、彼の死後、オランダは当時ヨーロッパ最強の軍事大国であったスペインとの八十年戦争を乗り切って完全独立を果たす事になる。
マウリッツはまた、将校を育成するための士官学校も創設した。この士官学校の卒業者の中には、後にバルト海一帯の覇権を握るスウェーデン王グスタフ2世アドルフに仕える者もおり、スウェーデン軍の強化は、この卒業生の功績によるものも大きいと推測されている。このように軍事史におけるマウリッツの影響は、オランダ一国にとどまらずヨーロッパ全体に広まった。加えてマウリッツは、軍隊にシモン・ステヴィン、ジャック・アローム等の優れた数学者・技師などを招き、新兵器の開発も振興した。
ヴァレンシュタインの軍事改革
ヴァレンシュタイン(独 Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein, チェコ語: Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, 1583年〜1634年)は三十年戦争期のボヘミアの傭兵隊長。神聖ローマ帝国の皇帝フェルディナント2世に仕えて帝国大元帥・バルト海提督・フリートラント公爵となって位人臣を極めたが、後に皇帝の命令で暗殺された。
従来の傭兵は現地調達、すなわち略奪を主に収入源として活動していたが、ヴァレンシュタインは軍税という形で収入を効率よく取り立てる方法を発見、活用した。これは占領地かその領主に対して略奪免除をする代わりに税金を取り立てそれを傭兵達の報酬に還元するというもので、諸侯や住民にとって重い負担なのは同じながら、直接土地に対する被害が無く確実な収入を見込めることから、このシステムを元に常備軍が出来上がりつつあったと言われている。
最盛期には12万5000もの大軍勢を率いていたヴァレンシュタインだったが、急速な出世と軍税負担から諸侯の反感を買い罷免されるに至った。再度の登板には皇帝側も徴税方法を学び取り独自に軍を集結させ、ヴァレンシュタインはその頂点に立ったといっても軍隊の忠誠は直接金を払う皇帝に向いていたため、暗殺時にほとんどの将校に背かれたことは彼のような自立した軍人の台頭は阻止・排除され、国家による軍事統制が始まったことを示している。
「銃剣(Bayonet)」の登場。
17世紀に入って「銃剣(Bayonet)」が登場すると、それまで槍兵に護衛されながらでないと戦えなかった銃兵が、自ら素早く白兵戦に突入可能となって兵の運用に柔軟性がもたらされた。語源はフランスの古都バイヨンヌ(Bayonne)とされる。
- スペイン国内のナヴァラ、フランス国内のガスコーニュ同様にバスク文化の影響が色濃い。現在のデンマークから840年にヴァイキングが到達。9世紀から10世紀にかけてヴァイキングの侵攻を継続的に受け続けた。その守護聖人たる聖レオンはノルマンディー地方カランタン出身で、10世紀にヴァイキングによるバイヨンヌ侵攻の際に殉教。しばしば切られた首を自ら手にして立っている姿で描かれる。
- アキテーヌ公領に吸収されていた1152年、女性領主であるアリエノール・ダキテーヌがのちのイングランド王ヘンリー2世と再婚したことにより12世紀から15世紀にかけてはイングランドの支配下に置かれ、スペイン国境に近い軍事的要衝でもあった事から英仏百年戦争(1337年〜1453年)の時代には激しい争奪戦が繰り広げられた。その影響で武器生産もさかんとなる。
- アドゥール川やバイヨンヌ港の整備が進むとタラ漁や捕鯨といった漁業およびその加工業で潤った。16世紀後半にはイベリア半島からユダヤ人たちがサンテスプリに移り住み、彼らがもたらした技術と知識によってチョコレートの生産が始まる。
- 17世紀に入るとこの地で起こった農民同士の紛争から偶然「銃剣(Bayonet)」が発明された。興奮した農民がマスケット銃の銃口にナイフを差込み、相手に襲い掛かったのが最初と伝えられる。当時のマスケット銃は有効射程が100m程度と短い上、装填にかなりの時間かかり発射間隔が長かった。それで射撃と射撃の合間に敵の歩兵や騎兵の突撃を受ける可能性が高く、一端詰め寄られたら近接戦闘の手段が剣しかないのでひとたまりもないので、銃兵は常にパイク(槍に似た長い棒状の武器)を装備する槍兵にを置く必要があったのである。しかし銃剣の採用により銃兵は敵の歩兵や騎兵の突撃を独力で迎撃することが可能となり、役目を失った槍兵も銃兵に更新する事で全歩兵が銃兵化され戦闘能力の向上につながった。
*例えばワーテルローの戦い(1815年)でも仏軍騎兵の突撃を受けた英軍の小銃手が方陣を組んで、銃剣を突出し槍衾とする事でこれを防ぎ切った。馬は訓練しても尖ったものに対して突っ込むことを恐れる為、この戦術は極めて有効だったのである。- 1854年にはパリと鉄道で結ばれ、ビアリッツで休暇を過ごす人々の観光拠点となった。20世紀に入るとフランコの独裁政権からの庇護を求めてスペイン・バスクが到来し小バイヨンヌに移り住んでいる。経済は一時的に低迷したが近郊のラックに油田が発見され、石油関連産品や周辺地域の農作物などの輸送の要として活況を取り戻しつつある。
現在は生ハム(復活祭の時期に見本市が開催される)やバスク伝統の仕込み杖(Swordstick)の生産、13世紀より7月から9月にかけてバイヨンヌ闘牛場で開催されてきた闘牛(フランス国内でも特に歴史が古い)で有名。また近年はサーフィンをはじめマリンスポーツのリゾートとしての再開発も進み、観光業も重要な収益源となっている。
- Swordstickの携帯は18世紀から19世紀にかけて欧州富裕層の間に流行したファッションでもあって、しかも女性にも人気で散歩用のステッキや日笠に仕込んだりしてたらしい(マラッカの木材の鞘とステンレス鋼の刃が最高峰だったそうな。どうやら18世紀に英国がインドを植民地化した結果、旧デリーのイスラム寺院の庭に立つデリーの鉄柱に驚異的耐候性をもたらすウーツ鋼が「再発見」され、十字軍の時代から憧憬の対象になってきたダマスカス剣への興味が再燃した事も背景にあるらしい)。ただし当時の技術では鞘の固定が不十分で事故が頻繁に起こっていた模様…
- こうした歴史があるにも関わらず、欧州においては「剣を振り回す女傑」の物語がそれほど広まらず、バトル・ヒロインの元祖を「武家の娘として小太刀も使いこなす」尾崎紅葉「金色夜叉(1897年〜1902年)」の実質上のメインヒロインたる赤樫満江(「ツンデレ」「逆パワハラ」「間接キス」「お嬢様笑い」「ヤンデレ・ループ」の元祖でもある)に持っていかれる展開を迎える。彼女のさらなる原型が当時欧米の女性小説界で一世を風靡していたバーサ・M・クレー「女より弱きもの(Weaker Than A Woman)」に登場するロリ毒婦マリア(金銭欲を満足させる為に金持ちの老人と結婚しつつ、若い愛人を得ようとする)なのは有名な話だが「結婚してるのに若い男を誘惑する」基本設定以外はほとんど残ってない。
そしてもちろん、日本で「銃剣(バヨネット)」といえば、」この人…
ここまでの話を整理してみましょう。欧州が 「(十分な火力と機動量を有する常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって養う)主権国家(Civitas Sui Iuris)体制」発祥の地を主張するのは、百年戦争(1337年〜1453年)を通じて概ねの国境を確定させたフランスと英国において時代に先行する形で「(資本主義的発展を阻害する)領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制」が駆逐されてきた歴史があるからです。
- 昔気質の軍事貴族はイングランドにおいては大貴族連合が「薔薇戦争(1455年〜1485年)」で互いに潰し合う形で、フランスにおいても「公益同盟戦争(1465年〜1477年)」や「フロンドの乱(1648年〜1653年)」で蜂起した帯剣貴族や法服貴族の内紛によって自滅を余儀なくされ歴史の表舞台から消え去っていく。
- とはいえフランス絶対王政は、その精緻さにおいて英国の責任内閣制に及ばずフランス革命(1789年〜1799年)による既存体制(アンシャン・レジーム)の徹底破壊と、サン=シモン主義に基づくイデオロギー再建を必要としたのだった。
*そしてそのサン=シモン主義を米国政府、ドイツ帝国、大日本帝国が模倣。第二次産業革命。
- 一方、軍役から解放された東欧の貴族達は再版農奴制を採用して農場領主化しながら(フランスや英国の貴族階層同様に)常備軍の将校や官僚の供給階層へと変貌を遂げていく。
とはいえこうした国々の多くは「(資本主義的発展を阻害する)領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制」からの脱却が不十分で共産主義国家化を余儀なくさせられたのだった。
もちろん、実際には同時期にハプスブルグ君主国(1526年〜1918年)や、オスマン帝国(1299年〜1922年)やムガル帝国(1526年〜1858年)も主権国家化を志向していたのですが、どうしても在地有力者連合が既得権益として金科玉条の様に掲げる「(資本主義的発展を阻害する)領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制」を打破する展開が叶わなかったのでした。
- 案外もっとも重要だったのは「大航海時代到来による経済中心地域の地中海沿岸文明圏から大西洋沿岸文明圏への遷移」だったのかもしれない。これによりオスマン帝国やムガル帝国や東欧諸国はそもそも最初から参加資格を失い、ポルトガルやスペインの脱落ばかりが強調される流れに。
- 三十年戦争(1618年~1648年)を終結させたウェストファーレン(Westfalen)/ウェストファリア(Westphalia)体制(1648年〜1803年)や、ナポレオン戦争(1803年〜1815年)を終わらせたウィーン体制(Vienna system/Vienna Settlement、1848年革命を経てクリミア戦争(1853年-1856年)によって完全に崩壊するまで続いた)といった国際協調体制の枠組みに参加する経験を有さなかった事も大きいかもしれない。カール・シュミットがその政治哲学の中で提唱している通り「国民」に多大な負荷を強いるこうしたシステムは、おそらく適切な仮想敵を設定した党争に勝利して国民統合に成功する形でしか実現し得ないのである。
こうして全体像を俯瞰してみると「(十分な火力と機動量を有する常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって養う)主権国家(Civitas Sui Iuris)体制」が「(資本主義的発展を阻害する)領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制」に完全勝利を納めたのは第一次世界大戦を契機に(ドイツ帝国や帝政ロシア同様に)やっとハプスブルグ君主国やオスマン帝国が解体された「(国家間競争が全てとなった)総力戦体制時代(1910年代後半〜1970年代)」以降であり、しかもその期間も「(資本主義的発展を阻害する)領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制」が伝統的に幅を利かせてきた(その状況を打破する為に共産主義を受容した)後進国ではFollow-Up運動が継続していた事になってしまうんですね。